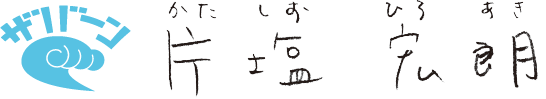箱根駅伝の往路は5区で逆転した青山学院の優勝でした。2位の中央とは1分47秒、ライバルと目される3位駒澤とは3分16秒、5位國學院とは5分25秒の大差をつけたため、明日の復路も青山学院が優位にレースを進めて大差で総合優勝を勝ち取る予感。出雲駅伝や全日本大学と違い10人で217.1kmを走る長丁場の箱根駅伝では総合力で勝る青山学院が強い。
この往路だけでも区間新記録を4人(2区3人と5区)が出すなど、ここ10年あまりの長距離界の急激なレベルアップは目を見張るものがあります。その一因となっているのがシューズの進化。かつてランニングシューズといえば薄ければ薄いほど良い!軽ければ軽いほど速い!とされていましたが、NIKEが2016年に世に送り出した厚底シューズでその常識がひっくり返りました。
発売当初はNIKEがほぼ独占していた厚底シューズも最近ではそのシェアは年々低下し、薄くて軽いでお馴染だったasicsがシェアを奪い返しているそうです。
箱根駅伝におけるシューズのシェア率は2017年大会でアシックスが31.9%でトップだった。しかし、その後は厚底シューズを投入したナイキが年々シェアを拡大していく。2021年大会は210人中201人がナイキで出走した一方で、アシックスはまさかの0人。箱根路から姿を消したことになる。それでも2022年大会で盛り返す。シェア率を一気に11.4%まで取り戻したのだ。
その後もアシックスは着用者を増やしていく。2023年大会では15.2%にアップした。前回となる2024年大会には24.8%まで引き上げ、ナイキ(42.6%)に次ぐ2位まで浮上。2025年正月の箱根駅伝はトップを狙える位置につけている。
さすが、「本気ならアシックス」のasics。今年の箱根でもMETASPEED EDGEが目立ちましたが、それ以上に多かったのがadidas。NIKEもまだまだ健在なご様子。今後の三強の争いも楽しみです。
シューズの進化だけではなくトレーニング環境や指導者の質の向上も大きな要因だと思います、むしろこちらの方が選手育成の貢献度は高いかもしれません。なんせ昭和時代は水を飲まないことこそが大正義のトレーニングでしたから。あの頃の未来である現在の頭で考えたら水を飲まずに激しいトレーニングをするなんて百害あって一利なし、そんなことをさせる指導者はとんでもない非常識パワハラ野郎となるわけですが、当時はそれが理不尽であることも込みで、当たり前の「常識」として受け入れていたので疑問すら抱けませんでした。
「常識を疑え」はスポーツに限らず、既成概念に囚われるな、といった意味で広告制作の現場でも好んで使われていますが、とても難しいです。みんながみんないちいち疑わずに生きるための物差しとして常識って作り上げられたわけですから。あの頃、水を飲むことも、厚底シューズでマラソンを走ることも非常識として誰にも見向きもされていなかったはずです。疑うべきは非常識の方にあるのかもしれません。今年の目標のひとつに「非常識を疑う」を加えてみようと思います。

駆け抜けろ、可能性。(asics)